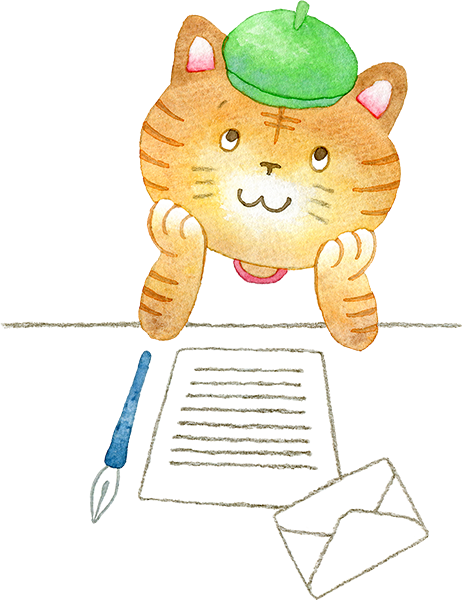不登校について(その2)

不登校への対応を考える場合、大切なのは「不登校は○○が原因だから、○○を治療すれば治る」式の単純な因果論で考えてはいけないということです。例えば「Aくんから意地悪をされて学校に行けなくなった」というとき、Aくんを指導して意地悪がなくなったからといって、すんなり登校が再開できるでしょうか。環境を変えるために隣の校区の学校に転校したとして、行けるようになるものでしょうか。友だちとのトラブルは、子どもの対人関係の自信を大きく損ないます。いじめを受けた子どもは、同年代の子どもと関わることに大きな不安を抱えるようになるのです。その状態で学校を替えたからといって、簡単にうまくいくわけがありません。それに、もしかしたら友だちとのトラブルには、この子自身の「相手の気持ちのとらえ方」にズレがあることが関係しているかもしれません。だとすると、そのまま新たな環境に飛び込んだとしても、また同じようなトラブルを起こしてしまう可能性があります。不登校に限らず、子どもの心の問題は、単一の原因で生じるものではなく、そこにはさまざまな因子が複雑に絡んでいるのです。
不登校に関係しやすい因子としては、大きく分けて、子ども自身に関わる因子(子ども因子)と、環境に影響される因子(環境因子)の2つがあります。
子ども因子とは、子ども自身がもともと持つ素因のようなものです。そのうち大きな影響を及ぼすものとしては、知的能力や発達特性、不安の強さなどの脳機能の問題と、起立性調節障害や過敏性腸症候群、アレルギー疾患などの身体的な問題です。学校は勉強をする場所ですから、学習困難の元となる知的能力や不注意傾向は、学校生活がスムーズに送れるかどうかに大きく影響します。また、学校での友だち関係の構築に影響するのが、自閉傾向や衝動性の強さ、不安の強さです。友だちと仲良くできるかどうかは学校生活の楽しさと密接に関係します。身体的な問題があり、具合の悪さから十分活動に参加できないと、子どもはだんだんと自信を失ってしまいます。
環境因子には、学校の問題と家庭の問題があります。例えば、学校でいじめられていたり、孤立していたりすると、学校生活は子どもにとって、とてもつらいものとなるでしょう。学級崩壊して教室が騒がしい状況だと、落ち着いて勉強したい子どもにとっては、毎日その場に通うのが苦痛になるかもしれません。その他、担任の先生とどうしても合わなかったり、担任の先生に過度に期待をかけられて負担に感じてしまったりする場合もあります。
子どもは学校で頑張った分、家でゆっくり過ごして元気を取り戻し、また次の日も学校に向かいます。もし、家庭内で言い争いが絶えなかったり、親が病気で子どもの世話を十分にできなかったりする状況があると、子どもは家で日々の疲れを回復することができず、だんだんと学校に向かうのがおっくうになってしまうのです。

これらの子ども因子と環境因子は独立して存在するのではなく、それぞれが影響しあっていることにも注意が必要です。学校で孤立しているのには、子ども自身の自閉傾向が影響しているかもしれません。いじめられるのには、家庭の経済的問題が関係しているかもしれません。起立性調節障害があって毎日頭が痛いのに、学校では学級崩壊していて騒がしくて、教室にいると頭痛がひどくなるから行きたくない、などという場合もあります。いずれにしても「1人の子どもが抱える因子は1つとは限らない」のだから「不登校の原因を1つの因子に結びつけてはならない」のです。
不登校の子どもに対応する場合、まず初めに「この子の今の状態には、どんな因子が関係しているのだろう」と考えます。そして、関係する可能性がある因子どうしのつながりから、子どもが現在の状態に至ったストーリーを自分なりに考えてみます。そのうえで「関わる因子のどこにならアプローチできるのか?」と考えを進めていくのです。もちろん、すべての因子にアプローチするのが理想なのですが、現実には扱える因子と扱えない因子があります。子どもに知的な問題や発達特性があれば、学校で支援学級や通級教室による支援を受けることが事態の打開につながる可能性があります。起立性調節障害のような身体的問題があれば、当然、生活指導や薬物療法などの医学的治療が必要です。しかし、家庭内でいざこざが絶えない、両親の仲が悪いなどという状況はおそらく変えることはできません。そのときには、子どもが元気を失わないよう相談を継続し、子どもの気持ちを支え、励まし続けるしかないのです。病気の家族がいて世話をしなければならない(ヤングケアラー)、経済的に困窮しているなどの家庭の問題は、福祉への相談を勧めますが、福祉の対応がスムーズに進まない場合もあります。学校での友だち関係のトラブルは学校に調整を依頼しますが、相手があることですので、思い通りに相手が変わってくれるかどうかはわかりません。自分以外の人には「変わってくれ」とお願いはできても、変わるかどうかは相手次第だということです。最終的には、自分自身が現実に折り合いをつけて動けるようになるしかありません。

ただし「動けるようになる」とは「行けなくなった学校に戻る」ということに限りません。家に引きこもるのではなく、勇気を出して外に出ることさえできればよい。それは、フリースクールでも、学習塾でも、放課後等デイサービスでも、中学卒業後ならアルバイトでもよいのです。
大人になったとき社会の一員として生活していくためには「自分ができる範囲で自分の役割を果たす」という意識が必要です。「学校に行けなくても、家で家族の一員として生活しているのであれば、せめて家族の役に立つように少しだけでもお手伝いをしよう」「誰とも会わないでいると、人と関わるのがどんどん怖くなるので、家から出て活動ができるようにしよう」と伝えます。また、将来に向けて最低限の勉強をしておくことも忘れないようにします。そのように少しずつ準備をしながら、どこかで、学校に限らず動き始める日を待ちます。とはいえ、ただひたすら待っていても子どもはなかなか動けません。焦って刺激するのはよくありませんが、適切な時期の情報提供や誘いかけは有効で、動き始めるまでの時間を短縮することができます。学校に行けなくなった当初は親子とも混乱し、どうしたらいいのかまったくわからず不安になり、言い争いが絶えませんが、子どもが学校に行けない状態を家族が「今は仕方がない」と受け入れると、子どもは徐々に落ち着きを取り戻していきます。「学校に行けない自分」を家族から受け入れてもらえていると感じることで安心し、少しずつ元気になるのです。そして、家の中で落ちついて穏やかに生活できるようになり、十分な時間が経過すれば、子どもは毎日をだんだんと退屈に感じるようになります。そんなときこそ「そろそろ外に出てみない?こんな場所があるらしいよ」という声かけのタイミングです。そうやって一歩を踏み出すことができ、外に出て家族以外の人と関わる機会が増えると、子どもはどんどん元気になっていきます。人は、自分以外の人からしか元気をもらえないのです。
学校に行けなくなったからといって、お先真っ暗なわけではありません。今の状態は「単に学校に行けなくなった」だけ。それ以上でも以下でもありません。そのように考え、将来への希望を失わず生きていく。それが、不登校の子どもと家族の支援としては、もっとも大切なことだと思います。
著者
| 著者 | 小柳憲司(コヤナギ ケンシ) |
|---|---|
| 所属・役職 | 長崎県立こども医療福祉センター副所長兼医療局長 |
| 長崎大学医学部、長崎大学教育学部、佐賀大学医学部、長崎医療技術専門学校非常勤講師 | |
| 専門領域 | 小児科学、心身医学 |
| 主な著書 | 身体・行動・こころから考える 子どもの診かた・関わりかた(新興医学出版社) 学校に行けない子どもたちのための対応ハンドブック(新興医学出版社) |
この記事の感想をお聞かせください
この記事についてのご意見やご相談等をお送りください。