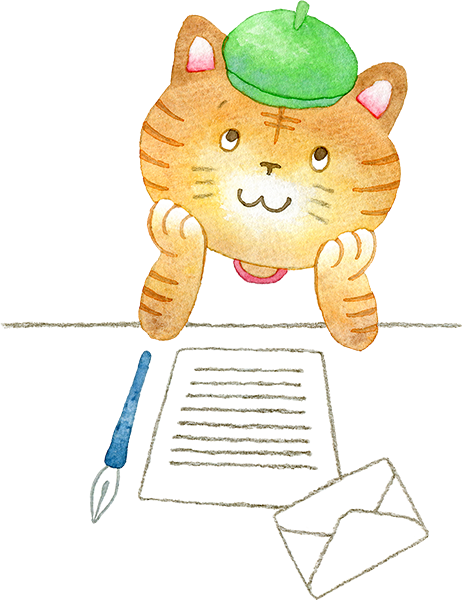まとめ(子どものこころの問題はどのように起こるのか~その考え方と支援の方向性)
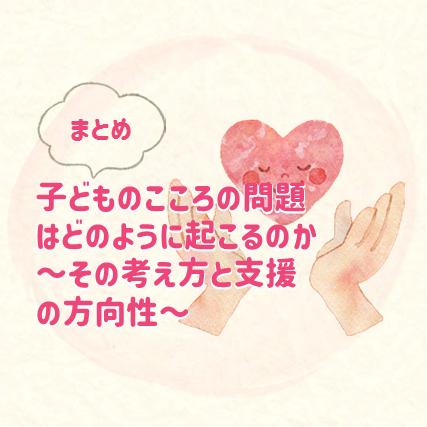
子どものこころの問題はどうして起こるのか。このシリーズの最後に、そのことについてお話ししたいと思います。医学において、いつも疾患は「素因と環境の作用によって起こる」といわれます。感染症でもそうですが、病原体が身体に入ってきても、病気を発症する人としない人がいます。病原体を受けた人の抵抗力が弱ければ発症するし、強ければ発症せず、逆に病原体をやっつけてしまいます。つまり、どのような場合でも、1つの要因だけでは病気は生じないのだということです。例えば、子どもが神経発達症(発達障害)の特性を持っていたとしましょう。発達特性は学校適応を危うくする大きな要因となりますが、だからといって、神経発達症の子どもがすべて不登校になるわけではありません。学校内の子どもたち全体の雰囲気や先生方の受け入れ、子どもと担任の相性などによって、学校への行き渋りが強くなるかどうかは決まります。このとき「素因=子ども自身の発達特性」「環境=学校での受け入れ」であり、素因があっても環境の作用で不登校状態が生じるか否かが決まってくるのです。ここでは学校環境を例に取り上げましたが、実は、環境の作用としてより大きく影響するのは家庭環境です。
子どもは基本、生まれたときから家庭の中で育てられ、家族との関わりの中で人間として成長していきます。家族から愛情をもって育てられることで「自分は周囲から受け入れられる存在なのだ」という基本的な安心感を身につけ、その安心感を元に子ども集団に所属し、人間関係を広げ、さまざまな体験を通じて自己肯定感を高めていきます。基本的な安心感や自己肯定感が、子どもが将来にわたって安定した人間関係を築く基礎になり、いろんな困難をやり過ごすストレス耐性を高めるのです。乳幼児期の子どもと家族の関係に問題があると、学童期・思春期以降の人間関係の形成に障害を及ぼす危険性があり、その最たる形が疾患としての「アタッチメント障害」であるし、社会的問題としての「子ども虐待」だといえます。
子ども虐待とは、保護してもらえる対象であるはずの大人から、子どもが暴言や暴力などを受けてしまうものです。いちばんわかりやすいのは、叩かれたり蹴られたりする身体的虐待ですが、大声で恫喝されたり「死ね」「生きる価値がない」など人格を否定されるような言葉をぶつけられたりする心理的虐待といわれるものが、通報としてはもっとも多くみられます。家族から性暴力を受ける性的虐待は、なかなか表面化しないため統計上の件数は少ないのですが、実際にはかなり多いのではないかといわれています。子どもが嫌がっているのにいやらしい話をしたり、性的な画像を見せたりするのも性的虐待にあたります。また、暴言や暴力はないけれども、まともな食事を与えず、入浴も着替えもさせない、子どもの話を聞かないなど、まったく養育を放棄している状況をネグレクトといいます。
このような状態に置かれた子どもが、周囲の大人から守られている、受け入れられていると感じられるわけがありません。ですから、虐待を受けて育った子どもは、暴力を受けて亡くなる危険性もさることながら、たとえ生き残ったとしても、将来にわたって周囲と安定した人間関係を築けなくなることが大きな問題なのです。
「虐待は家庭環境の問題だ。環境に問題があるなら環境を変えればいい。虐待する親のところになんか置いていたらまともに育たないのだから、親から子どもを引き離して別の場所で育てるようにすればよい」きっとそのように考える方もいるでしょう。しかし、世の中そう簡単にはいきません。客観的にみればどんなにひどい親だったとしても、子どもは「家からは離れたくない」と言うことが多いものです。「自分を生み、育ててくれた親から認めてもらいたい」やはり子どもはそう考えるのではないでしょうか。そして「家族と離れたくない」と言っている子どもを行政が無理やり引き離すのは人権侵害であり、やってはいけないことなのです。
虐待死のニュースをみると「なんてひどい親だ」と感じると思います。そういうケースがあるのは事実ですが、あくまでニュースになるのはセンセーショナルで珍しいことだからです。虐待したとされる人のほとんどは、別に子どもが憎くてたまらないわけでも、猟奇的に弱い人をいじめたいという人格異常者なわけでもありません。自分自身も追い詰められてイライラし、つい子どもに手を出してしまった、きつくあたってしまった、という場合が多いのです。そして、家族が追い詰められる1つの要因が子どもの発達特性です。「子どもがちょっとしたことでパニックを起こすので対応に苦慮している」「何度言っても同じことを繰り返すのでつい声を荒げてしまう」「学校で問題ばかり起こすのでしょっちゅう謝罪に回らなければならず気持ちが荒んでしまう」ということで、虐待につながってしまうのです。家族全体にコミュニケーションの難しさがあり、地域で孤立しているため、誰にも相談できずに家の中での虐待を防ぎきれないということもあります。そういうケースでは、家族も発達特性を持っていることがしばしばあります。つまり、虐待は家族だけの問題ではなく、子ども自身の問題や、地域の関わり方、学校の対応など幅広い問題が関わっており、単に「家族が悪い、家庭環境が悪い」という論調だけではまったく解決にはつながらないのです。
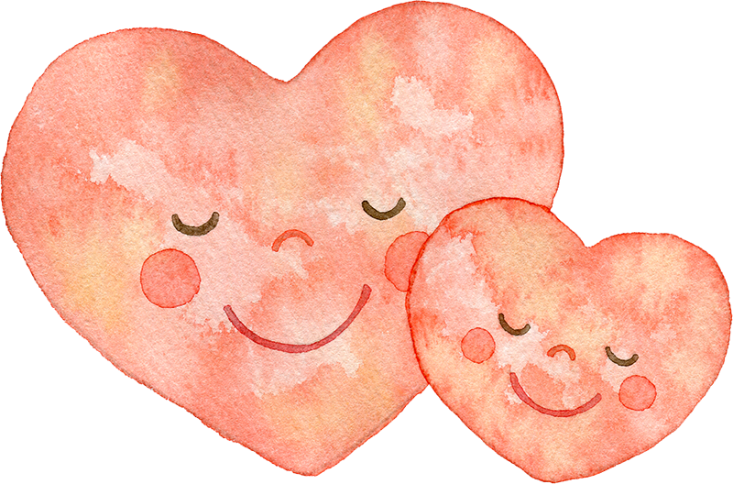
とはいえ、虐待ケースにおいて家族への関わりは必須です。家庭環境を整えるには、まずは家族の話をよく聴いて、家族が何に苦しんでいるのか、どうしてこじれてしまっているのかを洗い出します。家族も悩みに悩んで今の状況に至っているのですから、家族をダメ出しするのではなく「これまで大変だったですね」とねぎらうことが大切です。そのうえで、どこなら変えられるのかを考え、実現可能な提案をしていきます。できないことを無理強いしても何も変わりません。大切なのは「このようにしなさい」という指導ではなく「このような支援が受けられますよ」というアドバイスです。
子ども自身の発達特性にも問題がある場合には、学校に協力を仰ぎ、学習や学校生活における支援を検討してもらうことが子どものストレスを緩和し、家庭での安定につながります。家庭の経済状況が厳しい場合には、特別児童扶養手当や生活保護の受給を勧めるなど、経済的支援を行うことによって、子育ての心理的余裕につながります。
子どものこころの問題は、単一の原因では起こりません。どんなケースにおいても、現在の状況を形成する要因は複数あり、それらの要因自体も複雑に絡み合っています。そのことを理解し、単純な因果論に走らず、幅広い視野をもって考えるようにしましょう。そして、その中から現実的に可能な対応を選択するようにします。命の危険があるような場合を除き、焦りは禁物です。子どもと家族が納得しないと何も動きません。納得するまでは、介入しながらも変化を焦らず、時期が来るのを待つようにします。そのような姿勢が家族との関係を持続させ、いつか訪れる変化の原動力になるのです。

著者
| 著者 | 小柳憲司(コヤナギ ケンシ) |
|---|---|
| 所属・役職 | 長崎県立こども医療福祉センター所長 |
| 長崎大学医学部、長崎大学教育学部、佐賀大学医学部、長崎医療技術専門学校非常勤講師 | |
| 専門領域 | 小児科学、心身医学 |
| 主な著書 | 身体・行動・こころから考える 子どもの診かた・関わりかた(新興医学出版社) 学校に行けない子どもたちのための対応ハンドブック(新興医学出版社) |
この記事の感想をお聞かせください
この記事についてのご意見やご相談等をお送りください。